診療のご案内
診療日・時間について
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 ~ 13:00 |
● | ● | ● | / | ● | ★ | / |
| 16:00 ~ 18:30 |
● | ● | ● | / | ● | / | / |
| 18:30 ~ 19:30 |
/ | ● | / | / | ● | / | / |
★9:30~13:30
休診日:木曜、土曜午後、日曜、祝日
診療のご案内
- 当院はご予約の方を優先しています。
皆様の待ち時間をできるだけ少なくするため、できる限りご予約をお願いいたします。
初診の方はお時間を要しますので、時間に余裕をもってのご予約をお願いいたします。 - 患者様の状態や診療内容によって順番が前後することがありますのでご了承ください。
- 保険証を初診時は必ず、再診の方も毎月ご持参ください。
- 定期的に服用しているお薬がある方はお薬手帳かお薬自体をご持参ください。
- 他の精神科や心療内科へ通院中の方の転院希望の場合は、できるだけ紹介状、診療情報提供書をご持参ください。
- 自立支援医療を受けられている方は、受給者証と印鑑(シャチハタ不可)をご持参ください。
- 当院は院外処方になります。処方せんを発行いたしますので、お近くの処方せん受付薬局にてお薬をお受け取りください。処方せんの有効期間は発効日を含めて4日間です。
- 児童思春期(15歳以下)の方の診療につきましては専門外となりますのでご了承ください。
- 本人の受診が難しい場合、ご家族の方のみでの相談も受け付けています。
- 受付開始時間は診察開始の15分前(午前診:9時15分、午後診:15時45分。)、受付終了時間は診察終了の30分前(午前診:平日12時30分、土曜13時。午後診:月・水18時、火・金19時。)になります。ご注意ください。
- 不安なことやご質問があればお気軽にお問い合わせください。
ご予約、お問い合わせ: 072-246-9960
このような症状はありませんか?
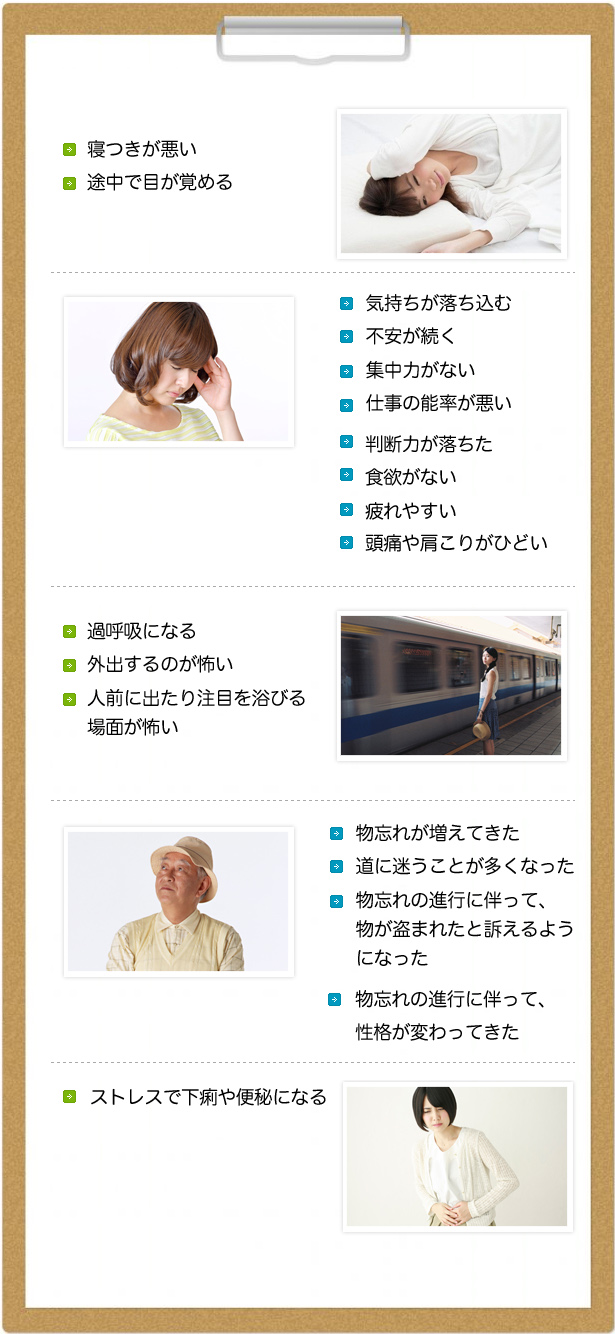
不眠症

寝つきが悪い(入眠障害)、途中で何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早くに目が覚める(早朝覚醒)、しっかり寝ても寝た気がしない(熟眠障害)、などから日常生活に支障が出てしまう病気です。
生活習慣の改善を行いながら、必要に応じて少量の薬物療法を行います。またうつ病など他の精神疾患によるものであれば、その原因疾患の治療も行います。
うつ病

ゆううつな気持ちや意欲が出ない、考えがまとまらない、自分を責めてしまうなどの精神的な症状と、眠れない、疲れやすい、食欲がない、頭が痛いなどの身体的な症状が続き、日常生活に支障が出てしまう病気です。決して本人の心の弱さが原因で起こるものではありません。
うつ病では、脳内にあるセロトニンやノルアドレナリンという心のバランスを保つ作用のある物質が減少していることがわかっています。
うつ病の治療で一番大切なのは心と身体の休息です。休むことに罪悪感を感じてしまい、休息をとらない方も多いのですが、まずはしっかりと心と身体を休めることが治療において重要です。また、症状のきっかけとなった原因がある場合はそれらの環境調整を行い、薬物療法として抗うつ薬という、セロトニンやノルアドレナリンを調整する薬を使用します。
そううつ病(双極性障害)

そう状態(気分の上がりすぎた状態)とうつ状態(気分の落ち込んでいる状態)を繰り返す病気です。うつ病と混同されがちですが、まったく違う病気で治療法も異なります。
割合としては、うつ状態の方が多く見られることが一般的で、当初はうつ病と診断され、経過中にそう状態が出現しそううつ病と診断されることもあります。環境面の調整に加え、気分安定薬などによる薬物療法を行います。
適応障害

学校や会社、家庭などの身の回りの環境等でのストレスにうまく対処できず、心や身体に様々な症状があらわれ、学校や仕事に行けなくなるなど社会生活に支障が出てしまう病気です。
特に周りの環境が新しくなったとき(進学、就職、結婚など)、新しい環境に馴染もうとしてストレスを感じ、心身のバランスを崩してしまうことが原因となります。
原因となる環境を取り除ければ症状は軽快することが多いです。環境の調整とともに、必要に応じて少量の薬物療法を行います。
パニック障害

前触れもなく動悸や過呼吸、息苦しさ、ふるえ、発汗、めまいといった発作を起こし、このままでは死んでしまうというような強い不安感に襲われ日常生活に支障が出てしまう病気です。
症状が強いため、「また発作が起きたらどうしよう」と不安になり、発作が起きやすい場所や状況を避けるようになります。特に、電車やエレベーター、渋滞している高速道路など、閉ざされた空間では「逃げられない」と感じて、生活活動の範囲が狭くなってしまうこともあります。精神療法に加え、発作の改善を目的として薬物療法を行います。
社交不安障害

大勢の人の前で話すなど、注目を浴びる場面に対して強い不安や緊張を感じ、ふるえや動悸、発汗などの身体症状があらわれ、いつも出来ることがスムーズに出来なくなる病気です。
性格の問題と混同される場合もありますが、社交不安障害ではそれらの行動に強い苦痛を感じ、身体症状が現れて、次第にそうした場面を避けることにより日常生活に支障が出てしまいます。精神療法に加え、不安の軽減を目的として薬物療法を行います。
認知症

年齢を重ねてくると、「うっかり約束の時間を忘れてしまう」「物をどこにしまったか忘れた」などの物忘れが増えてきます。
健康な人の物忘れの場合、「約束をしたこと」、「物をしまったこと」自体は覚えています。認知症の症状による物忘れは、「約束をしたこと」、「物をしまったこと」自体を忘れてしまうのが特徴です。
認知症の中で約半数を占めるのがアルツハイマー型認知症です。初期の症状として、最近のことを忘れてしまう「記憶障害」や、日付や時間や場所がわからなくなる「見当識障害」などがあります。病状が進行すると、性格が変わったり、「物が盗まれた」などの妄想も出現し日常生活に支障が出てきます。
早期発見・早期治療を行うことで、その進行を遅らせ、より長く有意義な生活を送るサポートをすることができます。病状とともに介護者の負担も増えてきますが、適切な対応を行うことで介護の負担を軽減できることも多いです。
統合失調症

およそ100人に1人がかかる頻度の高い病気です。実際にはない声が聞こえる「幻聴」や、事実でないことを事実であると信じ込む「妄想」などの症状が続き、日常生活に支障が出てしまいます。
できるだけ早期に治療を行うことが予後に影響すると言われています。脳内にあるドパミンやセロトニンなどの物質が関連していることがわかっており、それらを調整するため薬物療法を行います。
過敏性腸症候群

おもにストレスに起因して、下痢や便秘を慢性的に繰り返す病気です。検査を行っても異常がないにも関わらず、症状が続くことが特徴です。
試験前や大事な会議などの精神的ストレスや疲労、飲酒、喫煙、生活の乱れなどで引き起こされることが多いです。原因の改善とともに薬物療法を行います。
